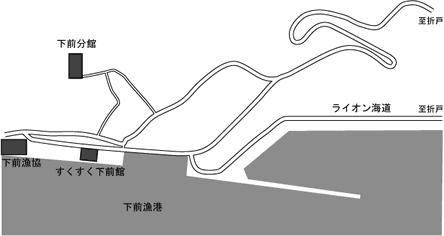平成19年度冬部(2)遺跡試掘調査速報!
昨年度に引き続き、小泊の歴史を語る会(柳澤良知会長)の協力を得て、塩釜と考えられる遺構の調査を行いました。今年度調査では、海水を煮て塩をとるための「土釜(塩釜)」跡ならびに海水を貯めておく「貯水槽」跡と考えられる遺構構造の一端が明らかとなりました。
「土釜」跡と推定される遺構は、貝殻・河原石と海水を練り合わせたセメント状の石灰粘土で作られており、移植ベラが刺さらないほど硬質です。径3~4m数畳程度の大きさのものが複数重なって見つかっていることから、何度も作り替えられた様子がうかがわれます。釜縁と推定される遺構も検出されました。
「貯水槽」跡と仮定した遺構は、大きな河原石を石垣のように組み合わせた精巧なもので、水が漏れないようにしっかりと粘土で覆われていました。
海側の部分が失われていますが、残された部分から8畳程度の大きさと推定されます。このほか海獣類と考えられる焼骨一体分も出土しました。
これらの遺構ではどのような塩づくりが行われていたのでしょうか。小泊地区における塩釜の記録は、貞享4年(1687)『陸奥国小泊村御検地水帳(弘前市立図書館蔵)』巻末の「但塩竈拾九箇所有」に遡ります。右の記事から少なくとも近世前期には、小泊地区の海浜において20釜近くが操業していた様子がうかがわれます。
その後も『御国日記』等を中心に記述が認められますが、近世後期から末にかけては旅人による紀行文が塩釜の様子を詳しく伝えています。 寛政5年(1793)三厩方面から小泊に入った水戸藩士木村謙次の「ヤカタ石ヒヨベオリコシ内ナト二里ハカリノ無人ノ地只焼塩ノ小舎二三所アル所ヲ経テ小泊ニ至ル(『北行日録』)」という記載をはじめ、寛政8年(1796)小泊を訪れた菅江真澄の「青岩ノ崎、屋形石などしほがまふたつ過ぎて(『そとが浜奇勝』)」ほかから、折腰内~矢形石間に小屋掛けの塩釜があったことがわかります。
とくに詳細な記録を残しているのが弘化元年(1844)に来訪した松浦武四郎です。紀行『東奥沿海日記』では
「此岬を廻て山に添て暫にシヲヘナイ 此処小湾にして上に田少し有。又海岸に小流有。側に塩がま有。年中此処にて汐を汲みて塩を焼くなり。その仕方一向世話のなき様成ものなれ共、薪は至て沢山に入るよし聞けり。焼方は備前辺にて焼様なもの也。又汐を汲ハ海中に櫓をかまひ、是に汲入トウユにて釜に来る様となす也。其仕方至簡なれ共、他国にては中々薪に引合がたしと思はるゝ也。又十七八丁も行。又二ヶ処有。」
と延べ、現在の「冬部」に比定される「シヲヘナイ」の塩釜に関心を寄せています。
松浦武四郎の記述からは、海中に組んだ櫓から浜まで樋を渡すことによって釜まで海水を導入し、いわゆる「海水直煮」によって製塩していたことが理解されますが、釜自体の構造については説明がありません。
一方小泊ではありませんが、今別・磯松の塩釜について同様の描写がある比良野貞彦『奥民図彙(天明年間)』では、「塩釜ハ土ニテ作ルモアリ又銅或銭釜 其処ニヨツテサマサマアリ 何モ大キサ九尺ニ六尺計ナリ」と、3畳ほどの大きさの土釜や金属製釜であったことを記しています。また同じ頃の黒崎(深浦町)の塩釜について言及している管江真澄も「このはまは海士、あななゐのたかきにのほりて、はねつるへして寄来る浪をくみて筧になかし、貝釜におとしいれて鹽やきたり。たれ潮てふものは、磯におまします神の好給はねは、みなかかる貝をねりてかまとなし、あら汐を其まま煎てけると。」と、やはり樋で海水を釜にかけ流す方法を説明し、塩釜は「貝釜」であるとしています。
以上近世諸記録からは、冬部の塩釜が近世の「土(貝)釜」である可能性が示唆されますが、果たして「土釜」とはどのような構造だったのでしょうか。北林八洲晴氏は、『日本塩業大系』所載の史料を引きながら、明治時代三陸沿岸の土釜の製作方法を次のように説明します。
土釜(焼貝殻粉粘土釜)
土釜の分布は、東北、北陸、関東、東海すなわち東日本の海岸で、東京湾を除くと直煮製塩ないし自然浜の地域に分布した。沿革については、東京湾では天正19(1591)年以降ということになっており、その発生については明白でないが近世から明治期まで用いられたことは明らかである。構造は釣釜の形態で、原料は蜆、浅蜊、蛤、あかざら貝、帆立貝、牡蠣、鮑などを焼き、粉末にし、これに苦汁あるいは鹹水を加えて粘土化したもの。大きさは縦横4mを大とし、小は4mに2.8mほどのものである。
土釜(焼月殻粉粘土釜)の釜と竈
材料となる貝殻は一昼夜蒸し焼きにして搗き砕き、粉末とする。1釜分に使う貝殻は4斗五升入り俵9俵すなわち約4石(721.56㍑)必要であった。そして粉末は海水、苦汁あるいは鹹水を加えて練り、石灰粘土とする。東京湾ではこれのみで、敦賀若狭では土を混じ、北陸方面では小石を混合した。
①竈 竈は灰と苦汁あるいは鹹水を練り、あるいは古釜を壊して海水でこねて築いた。大きさはその予定する釜の大きさと同じであるが、周囲の高さは約30㎝ほどであった。内部構造はよく分からないが、東京湾のような大型のものであれば灰出し溝を造ったものもあったと思われる。竈の上に釜を密着させて造ることは石釜の場合と同じで、その方法も基本的には同じである。
②釜 まず、竈の上に15cm角根太を3本縦に並べ、上に幅10㎝ばかりの板を敷き詰める。北陸では根太を2本の上に竹を並べ、更に茅簾を敷き藁を置いた。板の場合は上に鹹水を注ぎ灰を散布し藁を敷き更に枯れ草を敷き、その上全面を簀で覆った。この上に石灰粘土を塗りつける。厚さは約2㎝である。北陸では方3㎝に1個ずつの小石を並べ、小石の見えなくなる程度に粘土を塗り詰める。したがって厚みは3cm以上となろう。いずれも表面は打ったり摩擦したりする。終わると約30㎝間隔に経緯線を付け、釣金を植える。これの固定に平沼新田では水簸した粘土を用いたのである。この後、釜の周囲に高さ12cm、厚さ3cm、北陸では高さ9cmの釜縁を立てる。釜の平面形は東京湾では方型、北陸は楕円型ないし隅丸方型が一般的である。
釜の原型ができると焼き固める。東京湾では萱・篠などを燃料として表面を2回ないし3回(1回約4時間)、北陸では割木でもって一昼夜焼いていたようである。後は釣金を直し次に梁に釣る。この方法は石釜の場合と同じである。釣り終わると釜下に敷いた板・根太を抜き去り、その隙間を塗りこめる。この後は鹹水を釜に注入して約4時間沸騰させ釜造りを終わる。釜の寿命は行徳で約20日、大師河原で50~60日という。
(北林八洲晴 2003 『断章 青森の製塩跡考』)
これらから、土釜が明治時代前期まで使用されたこと、構造的に竈と釜に分かれること、木や竹・草本類等の心材に貝殻粉と海水等を練り合わせた石灰粘土を塗り固めて製作した吊釜であること、大きさは比良野貞彦等の記述に一致すること、耐久性1~2ヶ月程度であること、などがわかります。
|