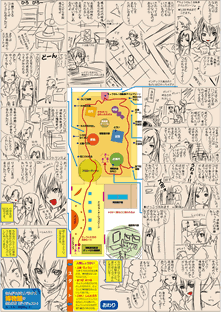|
博 物 館 ニ ュ ー ス |
| 過去の記事 1998年 9月 | 10月 | 11月 | 12月 1999年 1月 | 2月 | 3月 | 4-5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10-11月 | 12月 2000年 1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9-10月 | 11-12月 2001年 1-2月 | 3-4月 | 5月 | 6-7月 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 2002年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-11月 | 2003年 12月-1月 | 2月-4月 | 5月-6月 | 7月-8月 | 9月-3月 | 2004年4月-6月 | 7月-12月 | 2005年1月-5月 | 6月-8月 | 9月 | 10月-1月 | 2006年 2月-4月 5月-7月 | 8-12月 | 2007年 1月-7月 | 8月-9月 |
| 2007/11/20 | ||
北五地方における考古学研究の先覚者「北五六蔵」 北五地方とは、岩木川中下流部から竜飛崎までの範囲、現在の行政区域でいうと北津軽郡ならびに五所川原市域を指します。十三湊遺跡・五所川原須恵器窯跡などの国史跡を抱えるほか、オセドウ遺跡・笹畑遺跡・深郷田遺跡など縄文時代前期の標式遺跡も存在します。山内清男・白崎高保などの中央の研究者が考古学的な調査を実施したほか、早くから地元の研究者も活躍するなど、戦前から考古学がさかんな地域でした。 日本考古学の発祥は、1877年(明治10年)に東京大学で生物学を講じたお雇い外国人エドワード・モースによる大森貝塚の発掘調査に遡るというのが通説です。1884年(明治17年)には日本人類学会が成立し、その3年後には機関誌『東京人類学会雑誌』が刊行されますが、翌1888年(明治22年)には、早くも北五地方出身者の論文が誌上を飾ります。「陸奥津軽郡湯口村古物発見」と題する論文の著者は中泊町中里生まれの外崎覚蔵です。後には外崎覚とも称し、文部省維新資料取調員から宮内省に入り、「殉難録稿」編集、陵墓監、御用係などを勤めました。 また森鴎外の小説「澁江抽斎」に実名で登場することでも知られています。 外崎覚の父親は、藩校「稽古館」の助教を務めていた弘前藩士工藤他山です。「稽古館」を辞めた工藤他山は、嘉永年間中里村に隠棲し、地元の敦賀源次郎の娘磯子を娶りました。そして生まれたのが、次男覚蔵です。この外崎覚蔵が北五考古学研究者第1号となるわけですが、不思議なことになぜか北五地域の考古学研究者は「蔵(ぞう)」という名を持つ人が多いようです。外崎覚蔵を筆頭に、北五地域の代表的な考古学研究者6人「北五六蔵」を紹介しておきましょう。 外崎覚蔵の次の「蔵」は、五所川原出身の奥田順蔵です。奥田順蔵は、北津軽郡書記から飯詰村長となり10年在任、その後大正2年内潟村長となり、16年間在職しました。郷土史・考古学の研究者としても著名で、十三史談会・津軽考古学会を設立したほか、青森県歴史調査委員を務めるなど、北五地方の歴史研究に大きな足跡を残しました。津軽考古学会初代会長は奥田順蔵、副会長は今泉小学校校長等を勤めた教員福士貞蔵、事務局は武田村福浦出身の教員葛西国四郎というように、何れも中里に関係の深い人物が初期の津軽考古学会の中枢を占めていたというのは大変興味深いことです。 また奥田順蔵は、考古学者中谷治宇二郎と親交があったことでも知られます。中谷治宇二郎は石川県生まれ、東京大学人類学教室で学んだ天才的な考古学者でしたが、35歳の若さで亡くなりました。昭和3年夏7月31日~8月5日、当時内潟村長を勤めていた奥田順蔵は、相内村長三和五郎兵衛、板柳町出身の今井富士雄とともに、中谷治宇二郎を案内し、北津軽郡遺跡の調査を行いました。なお、板柳町出身の今井富士雄は、後に成城大学文芸学部教授となり、岩木山麓埋蔵文化財緊急調査特別委員会指導顧問・青森県文化財保護審議会委員などを歴任しました。 三人目の「蔵」は、奥田順蔵とともに「津軽考古学会」創設に尽力した五所川原出身の福士貞蔵です。もともと学校の先生で、先述したように今泉小学校の校長も務めました。「津軽考古学会」では初代奥田順蔵会長の跡を継いで二代目会長に就任し、『五所川原町誌』『板柳町郷土史』『鶴田郷土史』『金木郷土史』『津軽平野開拓史』等を著しました。そして4人目が、車力出身の秋元省三です。青森県文化財保護協会常任理事などを歴任、五所川原須恵器窯跡の調査に尽力しまた。「津軽考古学会会」では福士貞蔵会長の跡を継いで三代目会長となりました。 このほか、市浦村史を編さんした豊島勝蔵、北五地方ほか津軽地域の多くの遺跡を発掘調査した新谷雄蔵で「北五六蔵」が完成します。「北五六蔵」以外に特筆すべき郷土史家としては、例えば小泊の西山豊、市浦の佐藤慶司、金木の白川兼五郎、五所川原の太田文夫氏など様々な人々が思い起こされますが、地元中里では、神成平吉・小野勘六といった人々がいます。 神成平吉は、今泉出身の郷土史家で、神成商店経営の傍ら、奥田順蔵村長の勧めにより、今泉地区の由来や日常の出来事を詳細に記録し、それらの手記類は『内潟村史』『中里町誌』に多く採録されました。代表的な手記に 『今泉郷土史(一・二)』があります。また小野貫六は、内潟村出身でやはり奥田順蔵の薫陶を受けた人物で、昭和30年当時の内潟村長鳴海文四郎の依頼により『内潟村史』を執筆しました。昭和30年当時としては、出色のできであり、その後刊行された『中里町誌』もずいぶんと引用しています。 こうした神成平吉・小野勘六の仕事を受けて、満を持して刊行されたのが成田末五郎編『中里町誌』です。昭和40年、歴史・考古・民俗・産業・政治などあらゆる分野を網羅した近代的な町誌としては、青森県初となる記念誌的な文献です。 『中里町誌』刊行を企図したのは、当時中里町長を務めていた鳴海文四郎です。こうしてみてくると、中里地域の歴史・考古学研究は、二人の町村長、奥田順蔵が種をまき、鳴海文四郎が花を咲かせたということができるかも知れません。 |
||
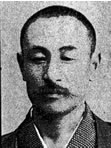   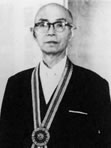 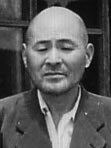  |
||
左から外崎覚蔵、奥田順蔵、福士貞蔵、秋元省三、神成平吉、小野貫六(内潟村史・五所川原市史ほかより) |
||
| 2007/11/6 | ||
小泊地区の「蝦夷館」の謎! 古代北奥地方、いわゆる「蝦夷」が居住していた地域では、空壕・土塁・柵列などの施設によって区画された集落が顕著に認められます。これらの集落は「防御性集落」などと称され、時間的には10~11世紀代に出現し、津軽海峡を挟んだ北奥・道南地域、すなわち郡制施行地域(国家領域)外に分布することが明らかにされてきました。 |
 |
|
中里城遺跡模型 |
||
現在のところ100ヶ所以上存在すると推定され、中泊町が位置する津軽半島においても、県史跡中里城遺跡をはじめとして、数多くの「防御性集落」が確認されています。津軽半島における北限の「防御性集落」は、五所川原市(旧市浦村)磯松川左岸に位置する古館遺跡であり、以北の小泊地区ではこれまで発見されていませんでした。ただし、 幕末小泊地方を訪れた紀行家松浦武四郎は、その旅行記『東奥沿海日記』に以下のように述べています。
小泊に「鍵掛勘ケ(解)由」「柿澤多門」「砂石兵部」という三ヵ所の「蝦夷館」があるという伝承を述べているわけですが、これらの地名は現存せず、具体的な比定は困難でした。ところが思いがけないところから突破口が開けました。『金木組村づくし』という小泊から下岩崎までの村々を歌詞に織り込んだ道中歌が『中里町誌』『小泊村史』などに掲載されています。
ここで目にとまったのが「鍵掛の坂」です。この道中歌からすると、「鍵掛の坂」とは、小泊から山中を通って上り詰めたところ、折戸の思案の坂とも称され、日本海を航行する船の帆が見える場所であることがわかります。そして折戸には「折戸遺跡」という古代集落遺跡が存在します。残念ながら、道路工事や避難所建設工事等によって全容が失われていますが、昭和54年撮影の空中写真で確認したところ、空壕状の低地に囲まれた平場ならびに半円状に取り巻く横壕跡のようなものが見えます。 平場東側の低地は、現在現在国道339号線となっていますが、当時は水田だったことがわかるとともに、平場東端沿いに旧道が延びています。国道339号線工事によってだいぶん勾配はゆるやかになりましたが、かつては小泊から旧道をのぼって頂点に達すると、日本海に浮かぶ岩木山が望めたとされます。避難所建設工事に際しては、平場を対象とした試掘調査が行われ、数軒の竪穴住居跡や土師器 |
||
・須恵器・擦文土器・鉄滓などが出土しています(青森県教育委員会第247集)。 遺物の年代からは10世紀後葉~11世紀前葉とみられ、壕跡が共存するとすれば津軽半島最北の「防御性集落」となります。「鍵掛勘ケ(解)由」なる「蝦夷館」は折戸遺跡を指している可能性が高いのではないでしょうか。 |
 |
|
 |
||
 |
||
折戸遺跡実体視写真/国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省「国土情報ウェブマッピングシステム」http://nlftp.mlit.go.jp/WebGIS/index.html より作成 実体視のコツ:20~30㎝離れて、垂直に写真を見てください。その際左写真は左目で、右写真は右目で見るようにします。そのうち立体像が浮かび上がります。 |
||
| 2007/10/26 | ||
大沢内溜池東岸においてナラの巨木発見! 現在大沢内溜池東岸では、県による森林整備事業が継続しています。作業道設置や苅払いが進むなか、偶然ナラの巨木が発見されました。樹高約25m、幹周は4~5mくらいありそうです。ナラは製品や木炭などによく利用され、こんなに大きくなるまで伐採されないのは稀だとか。 天に向かって、枝葉が広がる様はまさに「森の神」そのものです。その威容を見るにつけ、思い出されるのが「大沢内溜池の謎の吠え声」です。江戸時代後期、大沢内溜池を通り過ぎた紀行家管江真澄は、その大きさに驚きつつ、一種の怪異譚を紹介しています。春先、大沢内溜池のほとりで牛の吠えるような声が聞こえ、その正体は柳の大木の上にとぐろを巻いて眠っていた大蛇のいびきだったとする話しです。その姿を見た人は、身の毛もよだち、寒気がするとともに病に倒れたといいます(管江真澄『外浜奇勝』)。このような伝承は、柳の木よりも今般発見されたナラの樹こそ相応しいような気がします。 場所は、大沢内溜池東岸より西方へ突き出す舌状台地先端近くの斜面。従来は東回りに大幅な迂回ルートを取らざるを得なかったので行き来が大変でしたが、大沢内溜池公園から木橋が架けられたおかげで、手軽に見学することができるようになりました。私有林ですので、ルールを守って見学しましょう。 なお、ナラの木から徒歩約20分のところに、名水「湧きつぼ」があります。ブクブクと地中から湧き出る水はとっても新鮮で、よく冷えています。ひしゃくも用意されていますので、自由に飲むことができます。 |
||
巨木ついでに、ユズリ平の「千年松」も紹介しておきましょう。ユズリ平というのは、大導寺力伝説のある大導寺沢、中里城、宮野沢等へ通ずる古道が分岐する盆地状の場所で、戦後の一時期開拓が行われたところです。昭和36年室町時代の信楽小壺が採集されたのをはじめ、東側斜面から土師器や鉄滓が出土したことが『中里町誌』に記載されています。 何らかの遺跡であることは間違いなさそうですが、その古道沿いに一本の大きなクロマツがひっそりと佇んでいます。樹高約20m、幹周は3~4mで、「千年松」と称されています。由来については不明ですが、根もとに鳥居があり、石碑が建っています。「尊全堂、文化五戊辰年十月十三日願主敬白」という文字と馬の絵が刻まれていることから馬頭観音碑と考えられます。少なくとも江戸時代後期までは、馬が行き来する重要な街道だったのでしょうか。 |
 |
|
| 大沢内溜池「湧きつぼ」(約10秒、画面をクリックしてください) | ||
 |
 |
 |
大沢内溜池東岸のナラ |
天を衝く枝葉 |
巨大な幹まわり |
 |
 |
 |
大導寺牧場近くの千年松 |
威勢の良い枝振り |
足下には馬頭観音碑 |
| 2007/10/9 | ||
中里高校インターンシップ受け入れ!(9/11~13) 去る9月11~13日、青森県立中里高校学校2年生3名が、中泊町博物館ならびに図書館においてインターンシップを行いました。インターンシップとは、一定期間企業・行政機関等で研修生として働く制度であり、将来の仕事選びの参考とするものです。 日常の窓口業務から管理運営、各種活動まで一通りのメニューを体験してもらいましたが、博物館では夏の企画展の撤収から、梱包、資料登録・資料調査・土器復元ほか、教育普及活動の一環として「博物館マップ」づくりに挑戦してもらいました。 「博物館マップ」は、小中学生向けに、博物館の魅力や見所を記載したものであり、展示への理解や、伝達能力が問われます。難易度の高いメニューでしたが、三者三様すばらしいマップを制作していただきました。力作揃いでしたが、そのうち漫画仕立てのユニークな作品を紹介します。 |
||
 |
 |
 |
朝の開館準備 |
陶磁器の取扱 |
掛け軸の取扱 |
 |
 |
 |
民俗資料調査 |
調査カード作成 |
土器の復元 |